
昨夜、ツイッターを眺めていたら、「カーボンニュートラルは実現できると思うか?」というアンケートに大半の人が「できない」と回答していました。
このアンケートに何の意味もないことは確かなのですが、「世の中の意見とは、そういうものなんだな。」と改めて感じずにはいられませんでした。多くの人達は、目の前にある現実が全て・・・であることは、きっと、今も昔も変わらないのかもしれません。しかも、30年前に比べて、現在の日本人のほうが経済的に余裕がない人が多いはずなので、その傾向はさらに強まっているのかもしれません。
「カーボンニュートラルより、今日の稼ぎ」が大切なのは、十分に理解できます。「生活すること」「今を生きること」に全力投球することは何も不思議ではありません。だからこそ、「カーボンニュートラルは実現できると思うか?」と不特定多数の人達にアンケートをとることに、何の意味があるのだろうか・・・と思ってしまいます。
さて、唐突ではありますが、今では、誰もが当たり前のように、その存在を特に意識することもない「インターネット」の30年前を振り返ってみたいと思います。
30年前と言えば、1992年。当時、私は、京都の私立大学で情報工学の勉強をしていました。大学3年生の終わりに研究室に配属されて、ちょうどそのタイミングで研究室にインターネットがやってきました。京都大学と128Kbps(銅線の電話回線の4~5回線くらいの容量)の専用線で結ばれて、京都でインターネットが使えるのは京大とその大学だけらしいという話でした。しかも、お互いの情報工学科だけ。世の中の人達は、「インターネット」という言葉を全く知りませんでした。
最初は、私も、「パソコン通信と何が違うんだ?」としか思いませんでした。
自分たちで、htmlを書いてみて、「ふ~ん」「それで?」という感じでした。
ネット上にコンテンツもありませんでした。公的なコンテンツとしては、気象観測衛星「ひまわり」の地球の映像が公開されているくらいで、あとは、情報系の大学院生が作ったゴミ(?)が散乱している状況でした。それを、「モザイク」というブラウザでネットサーフィンするくらい。早稲田大学の「千里眼」というネットサーチのサイトがありましたが、ネット上にコンテンツがないので、その偉大さを理解できませんでした。
当時、私の通う大学には、NTTを退職して教授になった先生がいました。その先生が言うには、「光ファイバーなんて、普及しない。何十兆円もかけたら、NTTが潰れる。絶対に無理だ。」と理路整然と説明されていました。
でも、私は、「インターネット」や「光ファイバー」は普及するだろうなと思って、通信会社に就職しました。その後、ソフトバンクがYahoo!BBでADSLを販促し始めて、それを追いかけるようにNTTもADSLサービスを市場に投入しました。
そして、ADSLサービスと差別化を図るためと、電力会社が光ファイバーを市場に投入し始めたこともあって、NTTが光ファイバー網の整備に力を入れ始めました。それまでは、銅線の電話回線を使ってインターネット網にダイアルアップ接続していましたが、ADSLや光ファイバーでの常時接続が常識となり、やがて、「電話」はインターネット網に巻き取られることになりました。
並行して、モバイル通信も進化していくことになります。肩から担いで持ち歩いた大きな通信端末が、片手で持てるくらいに小さくなって、iモードの登場で携帯電話でもインターネットに接続できるようになり、それから、スマホも登場して。今では、インターネットが生活インフラであることを意識することさえなくなりました。
そんなインターネットの30年を振り返ってみると、「カーボンニュートラル」の実現も、きっと30年くらいはかかるんだろうなと思います。そして、今は「無理だ」と言っている人達も、30年の時が経てば、その恩恵を受けることになるでしょう。その人達が、それを認識しているのかどうかは別として。

2022/2/9
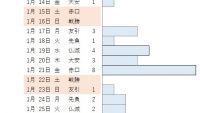
2022/2/8

2022/2/1

2022/1/31

2022/1/28

2023/3/9

2023/2/28

2023/2/16

2023/2/9

2023/2/1

2023/1/17

2022/12/8

2022/11/25

2022/10/19

2022/10/14
